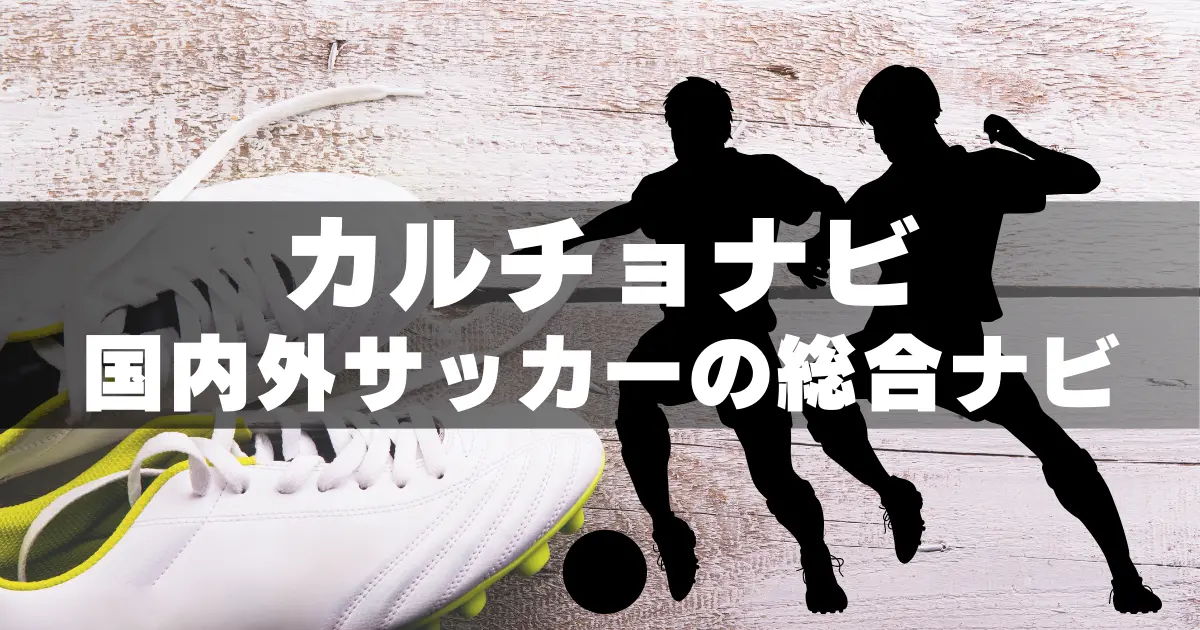サッカー観戦や子どもの試合の応援に行くとき、雨が降っていると「この試合、本当にやるのかな?」と心配になります。私も「降水量が○○mmを超えたら中止」のような明確なルールがあると思っていました。
しかし、Jリーグや日本サッカー協会(JFA)のルールを調べると、驚くべき事実が分かりました。実は、「雨量」を基準にした中止ルールは存在しないのです。サッカーは原則として雨天決行のスポーツです。
では、何が基準で中止が決まるのでしょうか。この記事では、雨量ではない「本当の判断基準」について、初心者にも分かりやすく解説します。
サッカー中止を決定するのは「誰」?
試合中止の判断基準を知る前に、そもそも「誰が」中止を決定するのかを知っておく必要があります。私が調べたところ、これは試合のカテゴリー(プロかアマか)やタイミングによって異なります。
試合開始後の絶対的な権限|主審の判断
一度試合が始まってからの「中断」に関する権限は、主審が持っています。サッカーの競技規則で、主審は競技規則の違反や外部からの妨害(天候悪化を含む)があった場合、試合を停止、中断、または打ち切る一切の権限を持つと定められています。
ピッチ状態の悪化や雷など、主審が「プレー続行は無理だ」と判断すれば、試合は中断されます。
Jリーグ(プロ)の場合|リーグとマッチコミッショナー
Jリーグのようなプロの試合では、主審が「中断」を決定した後、最終的な「中止(延期)」の判断は、主審単独では行いません。現場の責任者であるマッチコミッショナーの報告と勧告に基づき、Jリーグ(チェアマンなど)が総合的に判断します。
そこには、スタジアムの安全性、観客の安全な帰宅手段、今後の代替日程など、興行全体に関わる複雑な要素が関係してきます。
少年サッカー(アマチュア)の場合|大会主催者と会場責任者
一方、育成年代(少年サッカー)やアマチュアの大会では、Jリーグのような強固な運営体制はありません。多くの場合、その権限は大会主催者、具体的には「会場責任者」や「会場主任」にあります。
特に試合開始前の判断は、会場責任者が現地の天候やピッチ状態、気象警報などを見て決定することが一般的です。
中止基準1|ピッチコンディション(プレー続行可能性)
中止が判断される一つ目の大きな理由は、ピッチコンディション、つまり「サッカーを続けられる状態か」という点です。これは雨量ではなく、雨がピッチに与えた影響によって決まります。
「雨量」ではなく「冠水」が問題
大切なのは「降水量〇〇mmを超えたら中止」というルールではない、という点です。どれだけ強い雨が降っていても、スタジアムの排水設備が優秀でピッチに水が溜まらなければ、試合は続行されます。
問題となるのは、ピッチの排水が追い付かずに水たまりができる「冠水」状態です。ボールが正常に転がらず、サッカーという競技の本質が損なわれると判断されると、中止の対象となります。
主審が行う具体的な確認テスト|ボールは転がるか
主審がピッチ状態を判断する際には、世界共通の実践的なテスト(確認作業)が行われます。例えば、ピッチの複数の場所でボールを転がしてみます。
もしボールが水しぶきを上げてすぐに止まってしまったり、意図しない方向に不規則にバウンドしたりする場合、主審は「これはもはやサッカーではない」と判断します。この主観的なテストが、プレー続行か中断かを分けるラインです。
中止基準2|安全性の確保(絶対的な理由)
二つ目の基準は、ピッチ状態とは無関係に適用される「安全性の確保」です。これは選手、審判、スタッフ、そして観客の生命や身体の安全が脅かされる危険がある場合で、即座に中断・中止が決まる絶対的な理由です。
最も厳格な基準|落雷と「30分ルール」
天候に関する安全基準の中で、最も明確かつ厳格に定められているのが「落雷」です。JFA(日本サッカー協会)は「落雷事故防止のためのガイドライン」を策定しています。
このガイドラインでは、「雷の音が聞こえたら、即刻中断し、安全な場所へ避難する」ことが強く推奨されています。音が聞こえる時点で、雷はすでに危険な距離に接近していると判断されます。
試合の再開は、雷活動(雷鳴や雷光)が最後に確認されてから「30分以上経過」し、安全が確認された場合に限られます。これが「30分ルール」と呼ばれる基準です。
台風や強風による判断|暴風警報と飛散物リスク
台風や強風も、雨そのものより「風」による安全性の問題として扱われます。特に育成年代の大会では、試合会場が台風の「暴風域」に入ると予想されるだけで、予防的に中止が決定されることが多いです。
Jリーグの試合でも、スタジアム周辺に「暴風警報」が発令され、看板やテント、あるいはスタジアムの設備が強風で飛散・落下する危険性があると判断された場合は、中止となります。
暑さによる中止基準
悪天候ではありませんが、同じ「安全性の確保」という観点で明確な基準があるのが「熱中症」です。JFAは熱中症対策ガイドラインを定めています。
特に育成年代では、WBGT(暑さ指数)が「31℃以上」の時は、試合を開始すべきではない、という明確な基準が示されています。
プロとアマチュア(育成年代)で異なる判断基準
これまで見てきた基準は、Jリーグ(プロ)と少年サッカー(育成年代)で、適用の厳しさ(中止のハードル)が大きく異なります。私が思うに、これはそれぞれのカテゴリーで優先されるものが違うからです。
Jリーグ(プロ)はなぜ中止になりにくいのか
Jリーグが開催されるスタジアムは、そもそも排水設備が非常に優れていることが多いです。少しの雨では冠水しないため、プレー続行可能性の基準をクリアしやすいと言えます。
加えて、プロの試合は興行であり、放映権や過密な日程の維持も重要です。そのため、スタジアムの構造的な安全性が確保されている限り、中止のハードルは非常に高くなります。暴風警報下でもイベントだけを中止し、試合本体は開催された事例もあります。
育成年代で安全が最優先される理由
一方、少年サッカーなど育成年代の大会では、子どもの安全確保が何よりも最優先されます。JFAの安全ガイドラインに基づき、非常に予防的に(早めに)中止・中断が決定されます。
「雷の音が聞こえた」「暴風域に入りそうだ」「暑さ指数が高い」といった客観的な基準に基づき、会場責任者がリスクを回避するために早めの判断を下すのが特徴です。
中止になった場合の試合の扱い|再試合か抽選か
試合が中止になった後の扱いは、その大会のルールによって決まります。Jリーグや日程に余裕のある大会では、後日「延期(再試合)」となり、中断した時点のスコアや時間から再開されることもあります。
しかし、育成年代のトーナメント戦などで予備日が設定されていない場合、驚くかもしれませんが「抽選」によって次のステージへ進むチームを決める、というルールが採用されている大会もあります。
まとめ|雨でも慌てないために基準を知っておこう
サッカーの試合が雨で中止になる基準は、「降水量」ではありません。本当の判断基準は、「ピッチコンディション(プレー続行可能性)」と「安全性(落雷・強風)」という2つの軸で決まります。
特に「雷の音が聞こえたら即中断・30分ルール」は、プロ・アマ問わず適用される絶対的な安全基準です。
Jリーグが雨天決行しているからといって、子どもの試合も同じ基準で考えてはいけません。育成年代は安全が最優先されるため、中止の判断基準はプロよりもずっと厳しく設定されています。
私が応援に行く時も、これからは天気予報の雨マークだけでなく、雷注意報や風の強さ、主催者のアナウンスを注意深く確認しようと思います。これらの基準を知っておけば、急な中止決定にも「そういう理由か」と冷静に対応できるはずです。